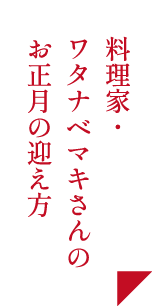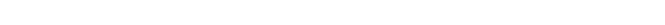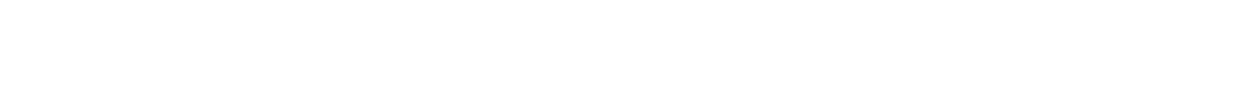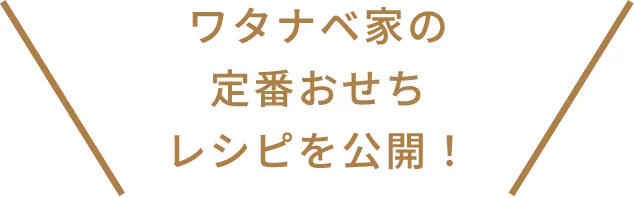Special Edition
2023.11.20
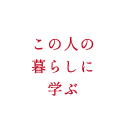

さまざまなテーマで生み出す
料理レシピはもちろん、
おしゃれなライフスタイルも
注目を集めるマキさん。
今回は、お正月の迎え方をインタビュー。
そこには、まねしてみたくなる
素敵な暮らしのヒントがありました。
●
巻末には、“ワタナベ家の定番
おせちレシピ”も掲載!
お正月料理の準備は
少しずつ、計画的に
忙しいからこそ、段取りよく
少しずつ仕込んで進めます
素材を生かし、手軽でシンプルなのに、おしゃれに決まるレシピが人気のワタナベマキさん。年に数冊の料理本を手掛け、テレビの料理番組や雑誌でもひっぱりだこ。旅好きで国内外の味に刺激を受けたり、興味のある料理の知識を学んだりと、いつもフル活動。そんな多忙なマキさんは、どんな風にお正月を迎えているのでしょう? マキさんの“いつものお正月”を伺いました。
準備は忙しさが増す年の瀬に、少しづつ進めていくそう。「12月になると、お正月の食材も増えてきますよね。お出汁用の昆布や鰹節、いりごまにごまめなどをそろえて、1週間前には、ごぼうや里芋、にんじんなどのお野菜を、30日にはブリや鯛なども買いそろえていきます」とマキさん。そして、おせち料理づくりは29日から、黒豆やなますなど時間をかけるものから仕込んでいきます。たとえば、のし鶏の肉だねを先に作って冷凍しておくなど、長年の経験による段取り力と、時間を上手に作りながら、準備を進めるのがマキさん流です。
新年に欠かせないのが“とっておき”の器たち。ハレの日には、特別なものをきちんと用意します。特に結婚時に購入したという折敷(おしき)や直線的な彫り込みが特徴的なお重、凛とした佇まいのお椀など、漆器を多用。「漆器は好きですね。長持ちするし、段々と育っていくところがいいんです」と話しながら、ひとつひとつ丁寧に拭き上げていきます。マキさんの“とっておき”とは、長く連れ添ってきたものたち。愛着のある器と一緒に新年を迎えます。

“とっておき”の器と1年ぶりのご対面。作家ものや骨董も加え、お正月用の器を選ぶのは気分も高まります。

お雑煮用のお椀も折敷も、丁寧に拭き上げて育ててきたもの。年季を重ねて艶も増してきました。奥は作家ものの和紙に漆を塗った小鉢。

おめでたい絵柄の銘々皿は、気に入って実家から譲ってもらったのだそう。菊の花を象った縁起の良い白皿は作家もの。
室内の設えは肩ひじはらずが、
マキさん流
玄関にお気に入りのしめ縄を。
部屋にも少しずつお正月仕様を取り入れます
ダイニングの中心は家族が集う丸テーブル。窓からはベランダのグリーンが広がり、愛猫のハットリくんも思わず日なたぼっこしてしまう心地よさです。そんないつもの空間を、花や飾りでお正月仕様にアレンジします。玄関には少しずつ集めているという、しめ縄飾りも。大がかりなものではなく、さりげなく、少しいつもと違うアレンジで演出するのがマキさんのスタイルです。

玄関で歳神さまをお迎えするのは、端正なしめ縄飾り。「これは、2人組のアーティストの作品。シンプルな形が気に入っています」

普段から緑を置く部屋のコーナーには、正月らしい枝物をさりげなく。皿の上では香木・パロサントをくゆらせて、気分もすっきりと。

20年以上使い続けていい色になった食器棚の上にもお正月の設えを。お花に鏡餅、お茶好きのマキさんのコレクションから選んだ茶器を並べて。「この鏡餅は磁器で、かわいいなと思って購入したんです。もちろん、食べられるお餅のときもありますよ(笑)」
大晦日の夕食は、仕込んでおける
シチューがお決まり
忙しい大晦日の夜はビーフシチューにワインが
わが家の恒例です
さて、大晦日。「うちでは大掃除は31日と決めてます」ときっぱり話すマキさん。「ただ12月に入ったら週末ごとに、引き出しだけとか、棚の普段やらないところまで拭いたりとか、ちょこちょことやっておきますね」と段取り力をここでも発揮。そして、おせち料理を総仕上げにかかります。
ときには義実家や実家のおせち料理を手伝いに行くこともあり、とにかく大忙しの大晦日の夕食はビーフシチューと決めているのだそう。「朝仕込んでおけば夕方にはできあがっているので、サラダやマリネを添えるだけ。気分的にも楽なんです」
いつしか大晦日のお楽しみになったビーフシチュー。「赤ワインとトマトだけで煮込んだ、ちょっと酸味をきかせたシチューは息子にも好評です」。夕方6時頃には準備を終えて、家族そろって食卓につきます。

おせち料理の準備も掃除も終えて、きれいに片付いたキッチンで。仕込んでおいたビーフシチューがいい具合いに完成。

牛すね肉はほろりと崩れ、無水で煮込んだ味わい豊かなシチュー。「夫も私もお酒が好きですね(笑)」。赤ワインを開けて、おいしいもの、好きなもので締めくくる大晦日。
元旦に、真っ白な
テーブルクロスを敷く
気持ちが引き締まる白いクロスと
特別な器で、新年を祝います
おせちやお屠蘇など、正月の習わしはいろいろありますが、マキさんがプラスして行うのが、元旦の朝、真っ白なテーブルクロスを敷くこと。ピシッとアイロンをあてたクロスを敷くと、その場がパッと明るい印象に。「毎年しますね。気持ちが切り替わるし、まっさらな気分で新しく始まる感じが気持ちいいんです」
ともすれば区切りのない日々でも、元旦は特別なもの。タオルなどのリネン類、そしてキッチンのスポンジも新年に新しいものを下ろすのだそう。一年の節目をきちんと大切にする、マキさんらしい、こだわりのひとつです。

白いクロスを敷くだけで、気持ちがすっと引き締まるよう。毎年欠かせない、儀式のようなものだそう。
おめでとうから始まる、祝いの朝がスタートします。

明るい陽射しに包まれて、清々しいテーブルに。2024年の元旦も新春日和でありますように。
家族で囲む、“わが家の定番”が
詰まったおせち料理
福を招くおせち料理は、佐賀で見つけた
とっておきの日本酒と
「作るのが大変でも、ないとさびしいし、やっぱり欠かせないもの」というマキさんのおせち料理は、彩りよく華やか。毎年少しずつバージョンアップして、今のスタイルになったそうで、定番はもちろん、家族のお気に入りが入った“わが家のおせち”。ベランダの南天の葉をあしらって、美しい盛りつけにも気を配ります。ちなみにお重でいただくのは元旦だけだそう。「二日からは漆の大皿などに盛りつけ直していただくようにしています」

クロスに映える、漆器と華やかな絵皿の組み合わせ。お屠蘇は骨董の銀色の酒器に、モダンなテイストのグラスを合わせて。ガラス器とのコーディネイトが軽やかな、マキさんらしいセッティングに。

ワタナベ家のおせち料理。のし鶏、錦玉子、五目なますは家族に人気の、外せない品。鯛の昆布締めのお寿司は菊花とイクラで彩り豊かに。
テーブルには佐賀の酒蔵のお酒も登場。仕事で全国各地を訪れることも多いマキさん。ラベルに鶴が描かれた1本は、お正月のお楽しみにとっておいたもの。この日のために準備をして、家族そろって迎えるお正月は、心地よい時間が流れていきます。

(右上から時計回りに)ごまをまぶしたのし鶏に、義実家の味だという錦玉子は、ゆで玉子の黄身と白身を裏ごしして蒸したもの。れんこんなますと、大根、にんじん、きゅうり、きくらげ、菊花が入った五目なます。「これに、金柑の甘煮も必ず入れますね」。最近のお気に入りだという佐賀・基峰鶴の生酒といただきます。
◎ワタナベ家の定番、のし鶏、錦玉子、五目なますのレシピは巻末に掲載しています。
「旅をするのも好きだけど、お正月は家で過ごしたい。
穏やかに、ゆっくり過ごすのが何より楽しみ」
というマキさんのお正月は、
無理せず、シンプルに、
マキさん流に整えられたもの。
取り入れてみたいアイデアもあちこちにありました。
来たる新しい年に、
いつもとは少し違う、新しいスタイルを加えて
お正月を楽しんでみませんか。
縁起のよいのし鶏には大好きなごまを。
卵焼き器でじっくり焼き上げます
のし鶏
材料(125×170㎜の卵焼き器1台分)
- 鶏ひき肉(もも)…400g
- 酒…大さじ1
-
A
しょうゆ…大さじ1
みりん…大さじ1
塩…小さじ1/3
溶き卵…1個分
片栗粉…大さじ2 - 炒り白ごま…大さじ2
- ごま油
作り方
- 1 フライパンにごま油小さじ2を熱し、ひき肉の半量を入れて炒める。肉の色が半分ほど変わったら酒をふり、汁気がなくなるまで炒める。バットに取り出し、広げて冷ます。
- 2 残りのひき肉に、Aを加え、粘りが出るまでしっかり混ぜる。1を加え、全体がなじむまで混ぜ合わせる。
- 3 卵焼き器にごま油小さじ1を熱し、2を入れて全体に広げ、表面を平らにならす。炒り白ごまをふって軽く押さえ、焼き色がつくまで4~5分焼く。フライ返しなどでそのまま皿に取り出し、卵焼き器をかぶせてひっくり返して戻す。弱火で10分ほど焼く。
- 4 皿やバットに返して取り出し、冷ます。食べやすい大きさに切り分ける。
“二色”=“錦”にちなんだ縁起もの。
ふんわり優しい味わい
錦卵
材料(161×113×51㎜の流し缶1台分)
- 卵…10個
-
A(黄身用調味料)
砂糖…大さじ2
塩…小さじ1/5
片栗粉…小さじ1 -
B(白身用調味料)
砂糖…大さじ1+1/2
塩…小さじ1/5
片栗粉…小さじ1
作り方
- 1 卵は常温に戻す。流し缶の大きさに合わせてオーブンペーパーを敷いておく。
- 2 大きめの鍋に湯を沸かして塩小さじ1(分量外)を入れ、卵を静かに加えて約13分ゆでる。冷水にとって冷まし、殻をむく。黄身と白身に分け、白身に黄身が残らないように、ペーパータオルできれいにふき取る。
- 3 黄身はボウルにザルをのせて裏ごしをする。Aを加えて混ぜる。
- 4 白身はフードプロセッサーでみじん切りくらいの細かさになるまで攪拌する。さらしで包み、水気をしっかり絞る。水気がなくなりホロッとなったらボウルに入れ、Bを加えて混ぜる。
- 5 流し缶に、4の白身を入れて隅までしっかり詰め、押して平らにならす。上に3の黄身の半量を入れて隅までしっかり詰め、押して平らにならす。残りの黄身はふんわりと、まんべんなくのせる。
- 6 蒸気が上がった蒸し器に入れ、6分ほど蒸す。蒸し器から取り出して冷ます。流し缶から出し、オーブンペーパーをはがして切り分ける。
紅白なますをアレンジ。
華やかで飽きのこない一品に
五目なます
材料(作りやすい分量)
- 大根…150g
- にんじん…80g
- きゅうり…1本
- 生きくらげ…3枚(60g)
- 生菊花…30g
- ゆず果汁…大さじ2
- ゆずの皮(せん切り)…2㎝角2枚分
- 塩
作り方
- 1 大根とにんじんは皮をむき、4~5㎝長さのせん切りにし、それぞれ塩小さじ1/3を加えてしんなりするまでもみ、約5分置く。
- 2 きゅうりは縦半分に切り、スプーンで種を取り除き、斜め薄切りにしてから4~5㎝長さのせん切りにする。塩小さじ1/3を加えてしんなりするまでもみ、約5分置く。
- 3 きくらげは石づきを取り、沸騰した湯に入れ約1分半ゆでて水気を切り、細切りにする。
- 4 菊花は花びらを摘んで、沸騰した湯に酢少々(分量外)を加え、1分ゆでて冷水に取り水気を絞る。
- 5 1、2の水気をしっかり絞り、3、4とゆず果汁を加えて和える。
- 6 全体がなじんだら、ゆずの皮を加えてさっと和える。
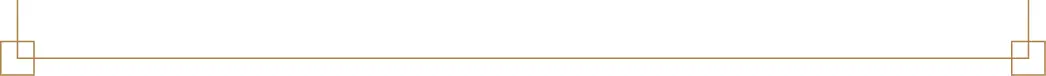
※表示価格はホームページ掲載時の消費税率による税込価格です。商品売り切れの節は、ご容赦くださいませ。
※記事に掲載されたイベント情報や商品は、掲載中または掲載後に売り切れ・変更・終了する場合がございますのでご了承ください。